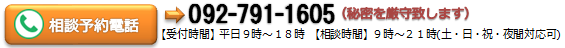労使問題
(1) よくある労使問題
会社は、従業員を雇用して事業をする以上、常に労使紛争が生じるリスクを負っています。残業代請求、人事異動への不満、パワハラ・セクハラ問題、労災等のほか、会社の状況によっては、労働条件の不利益変更や解雇をしなければならないこともあり、従業員との間で対立関係が生じます。
近年では、職場環境を巡る世間や従業員の目は厳しいものになっています。また、パートタイマー、派遣、高齢者雇用等、雇用の態様も様々になっています。社会の変化に合わせて新しい法規制や裁判例が生まれ、これまでと同じ対応で適切な対処ができる保証はありません。
人事労務に関する問題は、会社が一つ対応を間違えると、損害賠償請求、監督官庁による行政処分、社会的信用の毀損等、事業に重大な損失を与えかねません。他方で、紛争を防止し、円満な労使関係が構築できれば、会社の更なる発展に繋がります。
当事務所では、裁判例等の最新の動向も踏まえながら、各種規程の作成をはじめとする紛争防止のための人事制度の整備から、労働審判や訴訟などの実際の紛争処理まで、人事労務全般についてお客様をサポートいたします。
また、職場環境の問題、問題を起こした従業員に対する処分の問題、コンプライアンスの問題などに対応します。就業規則や労働条件通知書などの作成・変更もお任せ下さい。
(2)残業代請求未払問題
サービス残業とは、労働基準法で定められた残業代を支払わずに従業員に残業をさせることです。
従業員から未払残業代の請求を受けた場合、2年間分の代金を支払う義務があります。
サービス残業問題は、ときに会社が倒産しかねない大きな問題となります。
また、使用者がサービス残業の実態を知りながら措置を講じなかった場合、労働基準法違反として労働基準監督署から是正勧告を言い渡されます。この警告を無視して措置を講じなかった場合、労基法違反の疑いで検察庁へ書類送検される可能性があり、法人や代表者が罰せられる可能性もあります。
この残業問題の対策としては、労働時間の削減と残業代の抑制の2つの方法が考えられます。これらの方法によって、労働時間の抑制や、正規の勤務時間における業務効率向上といった効果も期待できるのではないでしょうか。
(ア) 労働時間の削減
① 残業の許可制
使用者の許可がなければ残業ができないようにすることが有効です。
具体的には、
ⅰ)残業が必要だと考えた場合、所定の用紙に残業時間・業務の内容等を記入して直属の上司に申請させる。
この時点で、明らかに不必要と思われる残業については、残業許可を出さない。
ⅱ)残業後、時間外勤務時間数を記入した用紙を上司に提出させ、本当に必要な残業であったのかを上司が判断し、承認を行う。
この手続を定着させる上で重要なことは、残業は上司の許可がなければできないというルールを社内で周知・徹底し、申請なしの残業を黙認しないことです。
② ノー残業デーを設ける
1週間のうち1日をノー残業デーとして、残業を一切認めない日を作ることも有効です。
(イ) 残業代の抑制
① 変形労働時間制
変形労働時間制を採用することで、法定労働時間を超えて就業させることができます。変形労働時間制には、1か月単位、1年単位、1週間単位のものがあります。
ア 1か月単位
1か月以内の一定期間を平均し、法定労働時間(1週間で40時間以下)に収めれば、特定の日や週について、法定労働時間を超えて労働させることができます。
この制度を導入するためには、就業規則に定めるか、または労使協定を締結して労働基準監督署長に届出をしなければなりません(労基法32条の2)。
常時10人以上を使用する事業所においては、始業・終業時刻を就業規則において特定することを義務づけられているので、就業規則において労働時間を特定しなければなりません。
また、常時10人未満の事業所であっても、労使協定による導入よりも、使用者に作成権限のある就業規則の方が導入しやすいでしょう。
ただし、労使協定にしろ、就業規則にしろ、単位期間内のどの週ないしどの日に法定労働時間(40時間ないし8時間)を何時間超えるかを特定しなければなりません(。
イ 1年単位
1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間を40時間以内に収めれば、特定の日や週が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするものです。
この場合は、1ヶ月単位の変形労働時間制より細かく規制されており、たとえば、以下の規制があります。
・1日の上限は10時間まで
・1週の上限は52時間まで
・週48時間を超える設定は連続3週以内(ただし単位期間が3
か月を超える場合のみ)
・対象期間を起算日から3ヶ月ごとに区切った各期間で、週48
時間を超える週は3回以内
・連続労働日数の上限は6日まで(繁忙な特定の期間は12日)
また、この1年単位の変形労働時間制を採用する場合、必ず労使協定を締結して、労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
さらに、就業規則においても、労働時間を特定しなければなりません。
ウ 1週間単位
業務の繁閑の激しい零細規模のサービス業、具体的には、常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店、飲食店の場合のみ対象となります。
この変形労働時間制も労使協定の締結と労働基準監督署への届出が必要となります。
この変形労働時間制では、1週間の各日の労働時間をあらかじめ、当該1週間の開始する前に書面により労働者に通知しなければなりません。
ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には変更しようとする日の前日でもよいとされています。
この制度を採れば、使用者は1週間40時間の枠内において、1日について10時間まで労働させることができます。
②定額残業制
これは、例えば、多くの残業時間が発生しているが、毎月の残業代計算が煩雑であるので残業代を定額としたい場合、所定の割増賃金に代えて一定額の手当を支払う制度です。
制度については、次の要件を満たす必要があります。
ア 通常の賃金部分と時間外・深夜割増賃金部分が明確に区別できること
イ 込みとなる時間を超えるときは、不足分を支払う合意がなされていること
この制度を導入する場合は、給与の中に残業を何時間分含めているか、含められている残業時間を超えて働いたときは、残業代を別途支払う旨就業規則・雇用通知書に記載しておくべきです。
③ 事業所外みなし労働時間制
従業員が事業所外で業務に従事している場合で、労働時間を算定しにくいときに所定労働時間だけ労働したものとみなす制度です。
この制度を導入するには、就業規則にその旨を定める必要があります。ただし、みなし労働時間が所定労働時間を超える場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」について、労使協定を締結しなければなりません。
なお、この制度は、「労働時間を算定しがたいとき」に限定されます。
④ 裁量労働制
これは、一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、遂行の手段・時間配分の決定等を労働者の裁量に委ね、労働時間については「みなし労働時間」を定めて労働時間を算定する制度です。
対象者は実際の労働時間が何時間であろうと、あらかじめ決められた時間労働したものとみなすことができ、残業代対策に非常に効果があります。
制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
(1)制度の対象とする業務
(2)対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
(3)労働時間としてみなす時間
(4)対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
(5)対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
(6)協定の有効期間
(7)(4)及び(5)に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
⑤ 振替休日の利用
本来、休日出勤の場合、休日割増手当(法定休日の場合3割5分増し)を払わなければなりませんが、休日の振替措置(振替休日)を行うことで、この割増賃金を支払う必要はなくなります。
ただし、以下の要件をみたす必要があります。
ア 就業規則等で休日の振替措置をとる旨を定める
イ 休日を振り替える前に、あらかじめ振替日を決めておく
ウ 法定休日(毎週1回以上)が確保されるように振り替えること
この要件のどれかが欠ければ、それは振替休日ではなく、「代休」になってしまい,割増賃金35%を支払う必要があります。
(3) 休憩・休日問題
ア 休憩時間
休憩時間とは、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間のことです。
休憩時間は労働時間の途中に設けなければならず、その長さは、
以下のように労働時間に対応しています。
・1日の労働時間が6時間未満の場合 :無くてもよい
・1日の労働時間が6時間以上の場合 :45分以上
・1日の労働時間が8時間以上の場合 :60分以上
イ 休憩時間自由利用の原則
時間の利用方法について、使用者が制限することはできません。
したがって、外出の制限も原則として不可であり、合理的理由があ
る場合に最小限の態様の規制(届出性、客観的基準による許可制など)をなしうるにすぎません。
休憩室で自由に休憩させつつ来客や電話に対応させることも、この自由利用の原則と抵触します。
ただし、業種によって、休憩時間の特例があります。
ウ 休日
使用者には休日付与義務が課せられており、原則として、1週間に1日、あるいは4週間に4日の休日を従業員に対して付与しなければなりません。
36協定(時間外・休日労働協定)を締結していないと時間外・休日労働をさせることはできません。
逆に言えば、36協定で定める範囲内であれば、法定労働時間を超えて労働させ、法定休日に労働させても、労基法違反とはなりません36協定は、労基署に届け出ることによって初めて効力が発生します。
(4) 解雇問題
経営者は、生産性を妨げる従業員は解雇して当然だと考えがちですが,
従業員を簡単に解雇することはできません。
普通解雇の場合、労働契約法第16条によって、客観的・合理的な解雇事由があり、かつ、社会通念上相当と認められないかぎりは、解雇したと
しても無効となります。
安易に解雇の手続きを進めてしまった場合、被解雇者との間で紛争を招きかねません。
したがって、解雇したい従業員がいる場合は、その解雇事由を慎重に検討するとともに、慎重かつ適切な手続きを行わなければなりません。
解雇の場合の注意点は、次の(あ)~(う)となります。
(あ)解雇事由の証明
解雇する際には、その客観的・合理的な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。
(い)任意退職・配転・降格・降給
たとえ従業員の能力が著しく不足している場合であっても,それだけを理由に解雇するのは困難です。会社と従業員が退職に合意した上で手続きを進める「合意退職」が、事後のトラブルを回避する解雇の方法としては有効です。
また、退職勧奨があり,使用者が労働者に対して「会社を辞めてくれないか」と申し入れ、労働者が応じれば合意退職となります。
合意退職にするには、会社が問題のある従業員に対して改善のための指導・教育を行っておくことが考えられます。ポイントとなるのは、「指導・教育の具体的内容」、および、「指導・教育を実施したことで当該従業員の就労態度や業務能力がどのように変化したのか」について記録を残しておくことです。
会社が当該従業員の退職を回避する努力を採ったのかは大変重要です。
指導・教育を施したにも拘わらず、当該従業員の就労態度や業務能力に変化が見られない場合は、配転(部署異動)の実施を検討すべきです。
それでも変化がない場合には、退職勧奨を行ったうえで、降格・降給を検討すべきです。
(う)解雇やむなしの場合
とにかく証拠を残しましょう。最初は,問題行動の改善を促すような文面で構いません。
2回目以降注意をする際には、今後改善されない場合には相応の処分を加えることを示唆する文面を加えるとよいでしょう。
解雇の可能性があることを示唆したにも関わらず、本人の態度に何ら改善が見られなかったことは、解雇の正当性を判断する上で重要な証拠になります。
(5)パワハラ・セクハラ問題
ア 実態調査
パワハラ・セクハラの相談や申告があれば、まずは実態調査を行って事実関係の把握する必要があります。調査を実施する場合は、「いつ」「だれが」「どこで」「何をしたのか」について記録するようにしましょう。
また、上司と部下との言い分が食違っている場合、メール等の客観的な資料の存在がとても重要となってきます。
イ 懲戒処分の検討
パワハラ・セクハラが認められた場合には、パワハラ・セクハラを行った従業員に対しては懲戒処分を検討すべきです。内容にもよりますが、まずは、譴責、出勤停止等の軽い処分等を過去の処分事例を考慮しつつ、就業規則に基づいて行うべきです。
ウ 人事異動
パワハラ・セクハラを行った従業員を別の部署に異動することも一つの手段です。
また、その従業員が管理職であれば、マネジメントの役割を果たしていないという理由で降格することを検討してもいいでしょう。
取扱い案件例
• 就業規則、賃金規程その他の規程の作成、チェック
• 労働者派遣、出向等に関する契約の作成、チェック
• 普通解雇、整理解雇、懲戒解雇を巡る紛争処理
• 従業員の労災事故への対応
• 割増賃金、残業代などの賃金請求を巡る紛争処理
• 問題社員に対する懲戒処分
• 人事労務に関するセミナー